満足するイベントにしたい~備えがあれば安心して臨めます
教えて!AIアシスタントの福田さん
AIアシスタントの福田さんが、オンライン配信に関する質問や疑問点にお答えします。
いよいよイベント開催当日です。すみれさんは少々緊張しながら、本番の注意事項について福田さんに確認したいと思います。
 すみれ
すみれ福田さん、ちゃんと準備してきたから大丈夫と思ってはいるのですが、いざ本番となると「トラブルがおきたらどうしよう?」とか「お客さん楽しんでくれるかな?」とか、いろいろ心配で…。
ここまで多くの人と時間が費やされてるし、みんなの期待も大きいので「失敗は許されない」というプレッシャーもあって。
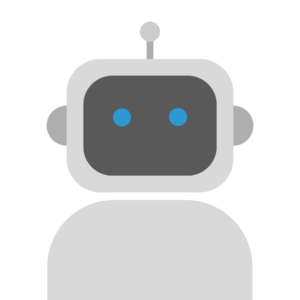 AIアシスタント福田
AIアシスタント福田すみれさん、そんな固くならずにリラックス、リラックス。
ちゃんと準備していればだいたい大丈夫です。
 すみれ
すみれえっ絶対じゃないんですか?
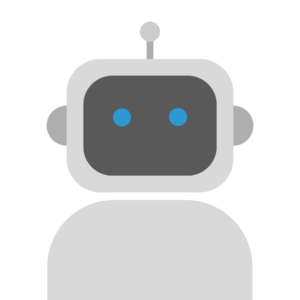 AIアシスタント福田
AIアシスタント福田インターネットを使ったシステムですから、突然トラブルが起こることはあります。他でも同じ障害が起こっているようならどうしようもないです。なので絶対とはいえないですが、できるだけ影響を最小限にしてイベントを進めることができるよう準備しておくことが大事です。すみれさん、今までちゃんと準備してきましたよね。
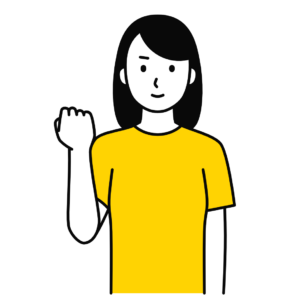 すみれ
すみれあっはいっ。そうでした。すっごい準備してきました。
ところで、本番当日はどんなことをしておけばいいですか?
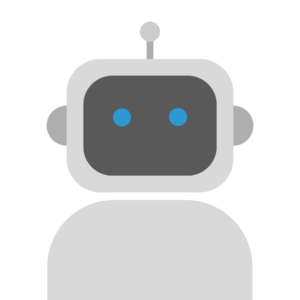 AIアシスタント福田
AIアシスタント福田ネットワークやPCなどの機器関連のトラブルは起きやすいものです。対策として、会場を設定する際に予備のネットワークや機器を準備して、トラブル時にすぐ切り替えられるようにしておきます。
 すみれ
すみれ全部の機器を二重化するってことですか?
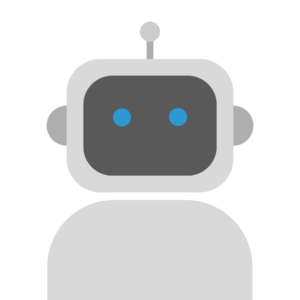 AIアシスタント福田
AIアシスタント福田全部ではなく、たとえば次のようにします。
インターネット:メイン回線とサブ回線を用意する。たとえば有線と無線、専用回線と共有回線、など系統が異なる回線を準備しておきます。サブ回線は多少スピードが落ちても構いません。メイン回線に何らかのトラブルがあっても、サブ回線は影響を受けていないという状況にしておきます。
PC:PCは必ず更新プログラムをあててアプリを最新にしておきますが、それでも動作が急に重くなるなどのトラブルが起こることがあるので、メインPCとサブPCを用意します。配信PCのメインとサブ、講演PCのメインとサブなど、どちらかがトラブルの場合すぐに切り替えられるように、サブPCもたちあげてメインPCと同じ画面がでるようにしておきます。切り替えに時間がかからないように、接続するケーブル等も準備されていると尚いいです。
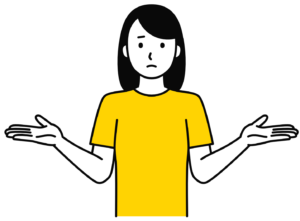 すみれ
すみれこういうのって準備に費用も手間もかかるので「無駄では?」と思う人がいるかもしれませんが、それでも必要ということですね。
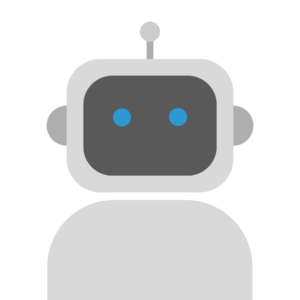 AIアシスタント福田
AIアシスタント福田そうです。確かにバックアッププランを発動することはめったにないかもしれません。でも何かトラブルが起こった時、それに巻き込まれる人、時間、労力などを考えると、バックアップを準備して、できるだけ短時間で乗り切れるようにしておくことが、結局はイベントの成功につながります。
 すみれ
すみれなるほど、心しておきます。
ところで、オンラインシステム自体にトラブルが起こった時はどうすればいいですか?
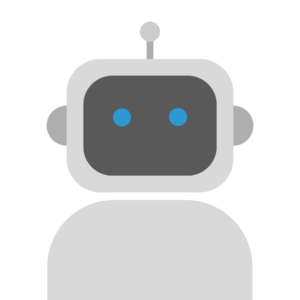 AIアシスタント福田
AIアシスタント福田うーん。それこそ早めに判断してお知らせしないといけないですね。選択肢はいくつかあります。
ハイブリッドイベントなら会場のイベントを継続して、もしビデオで撮影できるなら後で録画を見てもらうようにします。
もし他のオンラインシステムを使えるなら、別のオンラインシステムで予約した参加URLをお知らせして、全員に入り直していただくことができるかもしれません。
 すみれ
すみれどれをするにも、参加者全員に案内をしないといけないですね。
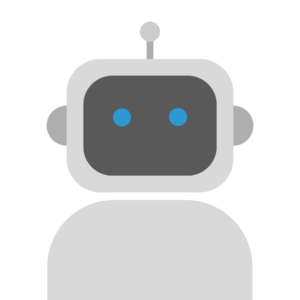 AIアシスタント福田
AIアシスタント福田まず、参加者に「トラブルが起きている」「今、対応している」ことを伝えます。これだけでも参加者は安心しますので重要です。参加者へアナウンスしたり、チャット等で連絡します。
幕間スライドに「トラブルが発生しています。復旧するまでしばらくお待ちください」とか「一度入り直してください」などの緊急用スライドを用意しておくとあわてずにすみます。
 すみれ
すみれまず、第一報ですね。
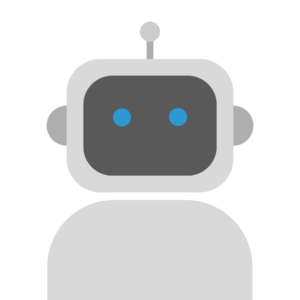 AIアシスタント福田
AIアシスタント福田次の方針が決まったら、イベント参加者に必ず届く手段…イントラネットやメール、SNSなどを使って参加者全員へ伝えます。全員に徹底するのは難しいでしょうが、できるだけのことをします。落ち着いて判断して事務局で手分けして進めます。
 すみれ
すみれこれこそ、メンバーの協力が必要ですね。では、会場で事務局メンバーや司会者がお互いに連絡をとるにはどうしたらいいですか?
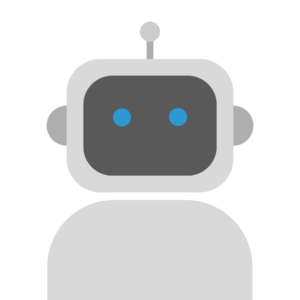 AIアシスタント福田
AIアシスタント福田インカムやトランシーバーのように会場内でお互いが話せるものがあればそれに越したことはないですが、ない場合は、関係者でオンラインミーティングや、グループチャットのようなもので連絡をとることができます。緊急を要する場合は音声の方が早く多く伝わるので、音声だけのオンラインミーティングはお勧めです。
 すみれ
すみれスマホでオンラインミーティングって、同じ会場内で音声で話したらハウリングしたりしないんですか?
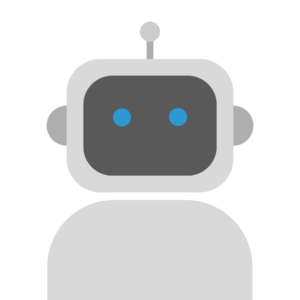 AIアシスタント福田
AIアシスタント福田イベントと同じ会議でなければハウリングはしないんですよ。別にミーティングを立ててください。ただ、両方の音声を聞かないとならないので、スマホにマイク付きイヤホンをつけて片耳で聞いて話すようにします。慣れていたほうがやりやすいので、一度試しておくことをお勧めします。
 すみれ
すみれ普段の積み重ねが役に立つんですね。
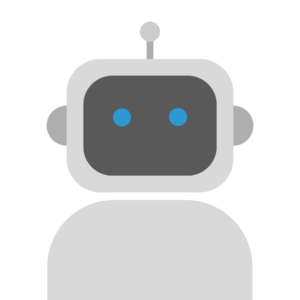 AIアシスタント福田
AIアシスタント福田その通り。いつもやっていることが、緊急時にも活きてくるんですよ。イベントがダウンしている時間はできるだけ短い方がいいので、短時間にスマートに、全員にちゃんとコミュニケーションをとって再開できれば、大きな不満にはならないはずです。
 すみれ
すみれわかりました!なんだか力が湧いてきました。みんなにイベントを楽しんでもらえるよう精一杯がんばります。
まとめ
- バックアッププランの必要性: イベント中に起こりうるトラブルに備え、インターネットやPC等機器のバックアッププランを用意することが推奨されます。
- コミュニケーション手段: 緊急時における運営メンバー間の連絡方法として、スムーズな情報共有のため、トランシーバーや口頭でのチームミーティングの利用が提案されています。
- 参加者への案内: トラブルが発生した場合、幕間スライドでの情報提供などまず何が起きているのか参加者全員へ案内します。









